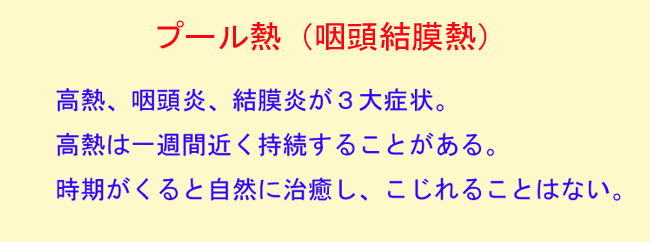- 家庭の医学 -
よく見られる子どもの病気
川崎病
川崎病は4歳以下の乳幼児に多い、原因不明の高熱と発疹を伴う熱性疾患で、皮膚粘膜リンパ節症候群(MCLS)と呼ばれることもあります。
年によって異なりますが、日本全体で年間数千~1万数千の患者が発生していると推定されます。川崎病は早期発見、早期治療が合併症(冠動脈瘤)や急死を予防するために重要です。
発病初期(2~3日目)に川崎病を見逃さないために
高熱と咽頭の発赤を認めるためにかぜと間違えられることがあります。しかし早いうちから頚部のリンパ節が著しくはれてくる特徴があります。
このリンパ節のはれは頚部の両側のこともありますが、多くは片側だけ著しくはれてきます。大きさはクルミ大くらいになることも多く、高熱とこのような著明なリンパ節のはれをみたときには、川崎病を強く疑う必要があります。
症状がそろい始めたとき
手足の指先のむくみと発赤は「テカテカパンパン」と表現されます。
さらにウサギのような赤い眼、口紅を塗ったような赤い唇が認められるようになります。(イラスト1)
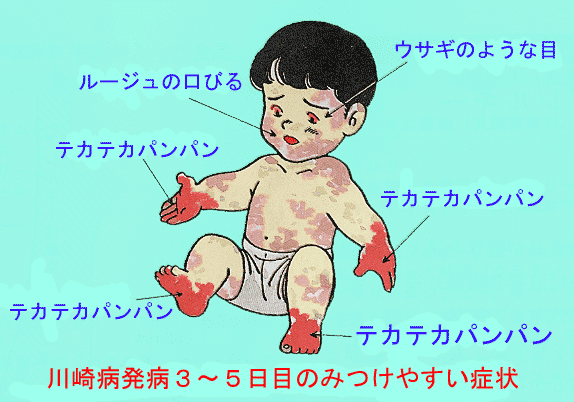
川崎病診断の手引き(旧厚生省川崎病研究班作成、1984年9月)から主要症状の項を抜粋してみます。
A 主要症状:
- 5日以上続く発熱
- 四肢末端の変化:(急性期)手足の硬性浮腫、紅斑。(回復期)指先からの膜様落屑。
- 不定形発疹
- 両側眼球結膜の充血
- 口唇、口腔所見:口唇の紅潮、イチゴ舌、口腔咽頭粘膜のびまん性発赤
- 急性期における非化膿性頚部リンパ節腫脹
*6つの主要症状をうち5つ以上の症状を伴うものを本症とする。
*ただし上記症状のうち、4つの症状しか認められなくても、経過中に断層心エコー法もしくは心血管造影法で冠動脈(いわゆる拡大を含む)が確認され、他の疾患が除外されれば本症とする。