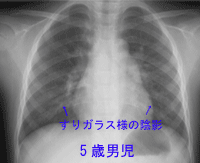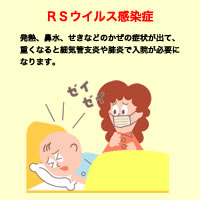- 家庭の医学 -
よく見られる子どもの病気
子どもの熱
子どもの発熱の原因を診断する上で、大人の発熱とは次に述べるような相違点があることに注意する必要があります。
- 子どもでは経過をみないと診断が困難な病気が多いこと
- 診断のために感染症の流行を知っておく必要があること
- いろいろな発疹を伴う感染症が多いこと
- 年齢によってかかりやすい病気に特徴があること
- 大人と違って血液検査やレントゲン検査が困難なため、治療や検査のタイミングが遅れるとこじれやすいこと
- 子どもは適切に自分の症状を訴えることができないこと
子どもが発熱を生じたときの診断の流れを注意点とともに述べてみましょう。
子どもの発熱の原因としてもっとも多いのは、かぜによるものでしょう。かぜの発熱はふつうは4日前後でほとんどが解熱します。
4,5日たっても解熱しない場合には、咳が多いときにはこじれて肺炎を起こしていないか、咳が少ないときにはかぜ以外の病気を考えていく必要があります。
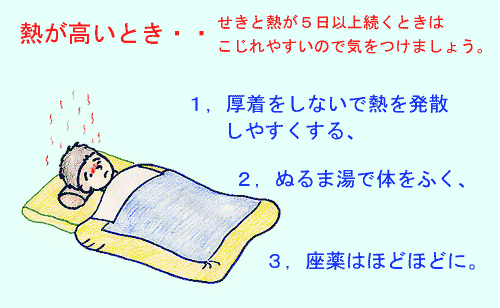
発熱時のポイント
- 子どもの発熱で咳が多くないときには、こじれる心配が少ないために安心して様子をみることができます。反対に咳が多いときにはこじれやすいので注意が必要です。
- 子どもの発熱で大切なことは、どのくらい高い熱が出るかよりも、どのくらいの期間熱が続いているか でしょう。
- 子どもの発熱が続くときには、一日おきに診察を受けるようにしましょう。そうすることによって適切な診断を下しやすくなります。
3、4日で解熱するとき
発熱の持続期間が3,4日以内で発疹を伴う場合には、1歳未満であれば突発性発疹症を、保育園などに通い、他の子どもと接する機会の多いときには、水ぼうそう、風疹、溶連菌感染症 などが考えられます。
1歳を過ぎた頃に高熱が3日くらい持続したあとに、口唇や舌に小さい口内炎が多発してきたときには、ヘルペス性歯肉口内炎と診断されます。
保育園児などで夏期に発熱と口の奥に口内炎を生じたらヘルパンギーナです。
耳の下やあごの下のはれが起こったときにはおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)や良性反復性耳下腺炎が考慮されます。
発熱以外にほかの症状がみられないときには、膀胱炎や腎盂炎などの尿路感染症が疑われます。(図2)
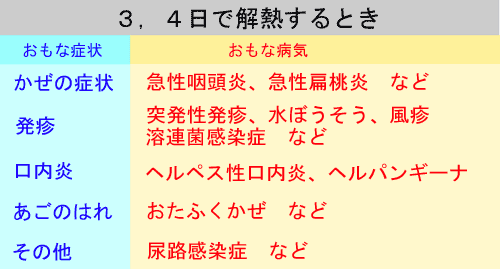
5日以上発熱が続くとき
発熱が4,5日以上持続するときには、かぜがこじれていたり、かぜ以外の原因で発熱している可能性も高くなり注意が必要です。
咳が多いときには、かぜがこじれて気管支炎や肺炎を起こしていないか、またマイコプラズマ感染症ではないか疑っていく必要があります。
血液検査や胸部レントゲン撮影が必要になるのもこの頃からと思われます。
またかぜの中でも夏期には、プール熱で代表されるように5~7日くらい高熱が持続するかぜが流行することがあります。
夏かぜのさいに、発熱が続くうちに頭痛とおう吐を起こしてきたら髄膜炎を疑う必要があります。(図3)
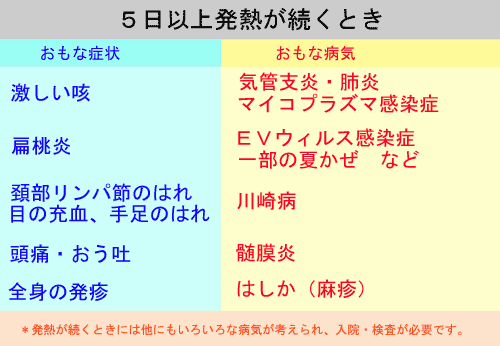
また発熱が持続し、全身の発疹を伴うときにははしか(麻疹)が考慮されます。
扁桃炎や頚部のリンパ節のはれがあるときにはEVウィルス感染症、特徴的な頚部のリンパ節のはれに目の充血、手足のむくみ、発疹などが加わると川崎病の可能性が高くなります。
原因不明の高熱と頚部リンパ節の大きなはれをみたときには、川崎病を疑い早期に入院させる必要があると思われます。
発熱を生じる原因は、比較的まれな病気として他にもいろいろと挙げられます。
外来診察ですべての発熱の原因を特定することは困難な場合も多く、4,5日以上発熱が持続するときには、検査などのために病院へ紹介することを考慮しながら接する必要があるものと思われます。